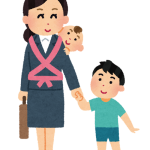女「せっかくだしコワイ話しない?」
女「そんなことは百も承知だよ。
けれど、今日は夏休み返上して学校に来てるのに会長である私と書記のキミしかいないんだよ?」
男「まあそれはそうですけど。
だからこそ少しでも打ち合わせをきっちりやっておいて次の議会で話がスムーズに進行するようにするべきなんじゃ」
女「家族旅行だの、塾だの、まあそりゃみんな忙しいのはわかるんだけどさ」
男「先輩だって今年、大学受験でしょ?
生徒会にウツツをぬかしてていいんですか?」
女「まあ高校生活最後の思い出作りなんだし、ハリキってもバチは当たらないと思うよ」
男「だったらその思い出作りのために話し合いをがんばりましょうよ」
女「それとこれとはべつなの」
2: :2013/09/03(火) 23:30:25.74 ID:
女「いいじゃん。なんせまだ午前中だよー?
私とふたりっきりでコワイ話しできるなんて嬉しくないの?」
男「いやその、なんていうかですね……」
男(オレとしては先輩とふたりっきりなのはかなり嬉しいことだ。
だけど、どうせならまだ十時過ぎなんだし昼までに会議を終わらせてメシ食いに行くなりなんなりしたいんだけどなあ)
女「もしかしてコイバナのほうがしたいとか?」
男「なんでいきなりそういう話になるんですかね。
顧問の……なんか名前忘れちゃいましたけど、先生がこの状況を見たらボクら怒られますよ?」
女「それなら大丈夫だよ。今日は先生も生徒会のほうじゃなくて部活のほうに行ってるらしいから。
私たちのジャマをする人はいないよ?」
男「……」
女「ね? いいでしょ? コワイ話させてよー」
女「もしかしてホラー苦手なの?」
男「んー、たぶんそんなことはないと思うんですけどね。
ホンコワぐらいじゃビビりませんよ、たぶん」
女「ふーん。まあ安心してよ。私の話は幽霊が出てくる話ばっかじゃないからさ」
男(なんだろ。今の言い方、まるで話がひとつじゃ終わらなさそうな感じなんだけど)
女「ほんとに大丈夫? 夜中に『うぇーん先輩コワくてねれませーん』とかならない?」
男「なりませんって。ていうか話早くしてくれないと帰りますよ?」
女「あーごめんごめん。おねがいだから帰らないでね」
男「じょーだんですよ。それで? どんな話を聞かせてくれるんですか?」
女「最初の話はね。ある女子大生が素敵なバイトをする話なの」
1
こみ上げてくる吐き気にみっともないと思いつつも道路にしゃがみこんだ。
襲いかかってくる嘔吐感をおさえるために深呼吸するも、都会のよどんだ空気はワタシの気分をより鬱蒼とさせるだけだった。
いっそのことここで全部もどしてしまおうか。そうすれば少しはらくになるだろう。
「サイアクっ……」
吐き出すようにそうつぶやいてふと、夜空を見あげる。
よどんだ夜空に取り残されたように雲がひとつだけ浮いていて、なぜかそれに奇妙な親近感を覚えた。
しばらくしゃがみこんでいたせいか、少しだけ気分がよくなった。
いつまでも道路にしゃがみこんでるのはみっともない、そう思ってワタシは腰をくあげた。
もちろん誰も自分のことを見ていないことなんてわかっていた。
少し歩くと電車が線路の上を走る音が聞こえてきた。
若者の街。
今ワタシがいる場所は一般的にそう呼ばれてる。
その名にふさわしい数の若い人間が夜中にもかかわらずあちらこちらにいた。
いったいコイツらはなんの目的があってこんなとこにいるのだろうか。自分のことを棚にあげてそんなことを思った。
ムダにでかい声でダベってる集団。
スマホをいじって壁によりかかってるヤツ。
うつむいたまま足早に駅に向かう人。
まあ、ワタシもはたから見れば同じように見えるのだろう。
実際ワタシはサークルの飲み会の帰りでこの街にいる目的なんてこれっぽちもなかった。
というか、サークルの飲み会になんて行きたくなかったのだからそういう意味では最初から目的なんてなかったのだろう。
本来ならトピック過多なキャンパスライフを送るワタシたちはそこそこに話すことはあるはずなのだ。
ましてサークルのメンツはある程度の馴染みがあるというのに。
やることと言ったら居酒屋の一角を陣取って時間と肝臓をすり減らすだけのアルコール摂取合戦。
満足な会話もせず、会話の代わりにジョッキをかわして煽られるまま酒を飲む。
あげくのはてに酔いつぶれて戻すもん戻してなんの意味があるというのか。
そしてそんなムダだとわかっていることを流されるまましているワタシはいったいなんなんだろうか。
いまだに足どりはおぼつかなかったけど、だいぶは気はまぎれてきた。
駅が近づくにつれて人が増えてくる。
道路をはさんだ駅の向かい側の道にはたくさんの店が一列に行儀よく並んでいる。
その店のひとつであるパスタ屋はワタシのお気に入りのところだった。
その店を食い入るように見ている女の子がいた。
遠目からだしワタシはそんなに目がよくないので断言できないけどたぶん、歳は同じくらいだと思う。
もちろんこんな時間だ。
すでに店は閉店しているし、そうじゃなくてもなんだかその女の子はヘンだった。
ただし、ヘンというのは女の子の外見が奇抜だとかそういう意味ではない。
むしろどちらかと言えばその女の子は地味でこれといって目をひくようなところはなかった。
女の子は店を正面を見ているのではなく、側面を見ていた。
より正確に言えば店の側面側の壁を見ているのだろう。
なにをそんなに真剣に見てるんだろ。
思わずワタシが足をとめたのとその女の子がそこから動き出したのはほとんど同時だった。
普段ならそのまま素通りしていくところだったが、ワタシはなにかに惹きつけられるようにそのパスタ屋へ行った。
小さいながらもシャレた外観をしているそこは女子にけっこう人気でたびたびワタシも友達ときている。
しかし側面側の壁を見たことはなかった。ちょうど女の子がなにかを見ていた位置と同じ場所に立ってみる。
壁にはなにかのチラシが貼ってあった。暗くて読めないのでスマホでフラッシュをたいて写真を撮ってみた。
どうやらバイトの広告のようだった。
ただしチラシに記された内容は、ふつうのバイトではないと思われるものだった。
主に十八歳以上の女子を募集しているみたいだ。
肝心なバイトの内容はデータ入力、とだけ書かれている。
より細かいことについては面接に来た人間にのみ教える、というものだった。
この時点でたぶん、大半の人はこのバイトに募集しないだろう。
「月、三十万以上….」
一瞬風俗かそれの類のバイトなのか、という考えがよぎったがチラシのはじっこのほうにそうではないという注意書きがあった。
もっともそれでこのバイトに募集しようと楽観できるほどにワタシの脳みそはお花畑ではなかった。
いつの間にかスマホの画面を食い入るように見ている自分に気づいて自嘲した。
「アホくさ」
いくら金がほしいからっていかがわしいバイトをする理由にはならない。
物騒な世の中なのだ。
自ら危険に飛びこむようなマネをすることはない。
一瞬だけそのチラシのあった場所をふりかえってワタシは街をあとにした。
2
「えっと、なにかバイトとかってしてる?」
「バイトですか?」
月曜の五限の講義をワタシは英語にしている。
正直義務教育からやっている英語に関してはいいかげん飽き飽きしていた。
けれどまだある程度はこなせるぶん、ほかのわけのわからない電波の羅列を垂れ流す教授の講義よりはいささかマシかもしれない。
もっともこの講義は大人数教室で内容もそんなに難しくないためほとんど集中して聞いたことはない。
そういう意味ではほかの講義となんら変わりはない。
そして、たまたまペアワークで隣りになった女の子に時間つぶしがってら聞いてみた。
バイトのことについて。
「個人経営のカフェで働いてますよ」
化粧っ気がほとんどなく、いかにも地方出身といった感じの地味な隣の女子はやわらかい口調で言った。
透き通るという表現がぴったりの白い肌から、この女の子はたぶん秋田出身なんだろうなあとかてきとーなことを考えながら会話を続ける。
「カフェかあ。いいなあ、ワタシ飲食やってんだけど時給安くてさあ」
「飲食店ってやっぱり大変ですよね? 私のところもそんなにお金高くないんですけど。
でもそんなにお客さん来ないんでらくなんですよね」
「ふーん。ああ、そんでね。
なにか新しいバイトさがそーかなって思ってさ。なんかないかな?」
「私、今やってるバイトが初めてで。だからあんまりバイト詳しくないんです」
「あ、そーなの? まあ言ってもワタシもそんなバイトしてないんだけどさ」
教授のボソボソした声をバックにワタシは昨日撮ったチラシの画像を見せてみた。
「これ見てみて。昨日たまたま歩いてたら見つけたバイトの張り紙なんだけど」
「さ、三十万……!? え? これどんなバイトなんですか?」
「ちょっと声でかいって。いちおう、今授業中」
「あ、すみません。ついびっくりしちゃって。
でもこれっていったいなんのバイトなんですか?」
「ワタシもたまたま見かけただけだから全然わかんないんだよね。
けど、やっぱり興味わくじゃん? こんだけ高給だと」
「……もしかしてこれって出会い系サイトのサクラのバイトなんじゃないんですか?」
「へ?」
不意にそんなことを言われてワタシはマヌケな声をあげた。
「あ、その、私もたまたまサークルの先輩から聞いただけなんですけど。
パソコンのデータ入力とかの募集ってそういうのが意外とあるらしいんです。
さすがにおおっぴらに募集できる内容のものじゃないからそういう風に募集してるらしいんです」
たしかに言われてみるとあのチラシもわざわざ店と店の間の目につかない壁に貼り付けてあった。
「実は私の先輩がサクラのバイトしてたみたいで。風のうわさで聞いただけなんですけど。かなりお金もらえるみたい」
「うーん、まあそりゃあね。特殊な仕事みたいだしお金たくさんもらえなきゃやる人間いないんじゃない?」
「犯罪に近い行為かもしれないですしね。でも少し面白そうですよね」
ちょうど教授がホワイトボードをたたいて反射的に前を向いたために、そのときの彼女の顔は見えなかった。
その代わり彼女の声に含まれたイタズラげなひびきはやけに耳に残った。
面白そう。
地方から上京して大学生になって一年と半年。
東京という街で起こるありとあらゆることがワタシには新鮮で魅力的で刺激的だったと思う。
ただワタシというニンゲンはどうしようもなくすべてのものごとに対して飽きやすかった。
というよりワタシという容器はこれまで生きてきた中でもっとも解放的で刺激的な生活の中で満たされてしまったのだと思う。
器を破ってしまうぐらいの刺激をワタシは欲しているのかもしれない。
「そのバイトするつもりなんですか?」
「さあね」
ワタシはあえてとぼけた。けれどもコタエはもう決まっていた。
人であふれる中央本線を通る電車も休日の昼間となればいくぶんかマシになる。
それでもワタシが住んでいた田舎町と比較すれば乗車率は圧倒的に高いんだけど。
現在住んでる自分の街から中央本線を利用してさらに御茶ノ水で総武線に乗り換えて、ようやくたどり着いたアキバの駅は人でごったがえしていた。
思わず人の多さにしかめっ面をしてしまう。
秋葉原には上京したてのころに暇つぶしと東京観光を兼ねて一回だけきたことがあった。
いかにもオタクといった感じの人が大半を占めているのかと思っていただけに当時は自分と同じような大学生が意外といることにおどろいた。
はっきり言ってワタシは人ごみは好きじゃない。
理由はよくわからないけど人がたくさんいるところはムダに騒々しいし、やたらに体力を浪費する。
だから池袋や渋谷、新宿と言った人が極端に集まる場所には基本的にはひとりで行くことがない。
付き合いでしかたなく行くことはかなりあるけどできるなら避けたいと思ってる。
都会の街を歩くときは自然と足どりが重くなる。
もっとも今日にかぎってはワタシの足は軽かった。
今日はバイトの面接だ。
あの地味ガールとの会話のあとワタシは講義をぬけてすぐに例のバイトの電話をした。
スマホを握る手が少しだけふるえたけど、電話越しの相手の柔らかい声を聞いたらそれもすぐにとまった。
にぎやかな街の中心から少し外れたとこの昭和通りをまたいで隅田川の方面を目指す。
さらに小さな路地に入っていくと古びたビルがある。そこが面接会場だった。
ビルじたいは小さくて看板があるわけでもないので特別目につくようなものでもない。
どちらかと言うと等身大のアニメキャラクターのパネルがズラッと並んでる隣のカレー屋のほうが断然目立つだろう。
電話の相手の言ったとおりだとしたらここで間違いはないのだが、少しだけワタシは不安になった。
「いや、でもまあ教えてもらった場所はたぶんここであってるしな……」
とか言いつつもワタシはビルをあおぐだけあおいで肝心の行動を起こせなかった。
「あの……バイトの面接に来た方ですか?」
「は、はい!?」
不意に声をかけられたせいで返事の声がひっくりかえってしまった。
視線を正面にもどすとワタシのお父さんと同じぐらいの年齢の小柄なおじさんが両手を擦り合わせて立っていた。
「あ、はい、そうです。
えっと….. わざわざ下にまで出迎えてもらってすみません」
「いえいえ。こちらこそわかりにくいところで申し訳ないです。
まあ、とりあえず中へどうぞ。すぐに面接をはじめましょう」
案内されたビルの中は予想外に不気味で無意識に息をのんでしまった。
ビルの廊下は薄暗かった。
天井の蛍光灯がついてないだけでなく窓もないから外の明かりも入らないせいだ。
歩くたびに舞うほこりにむせてしまいそうになるのをなんとかこらえてワタシは目の前を歩くおじさんについていく。
「ではここにかけてお待ちください。すぐに面接準備をしてきますので」
案内された部屋のパイプ椅子に腰をかけてワタシはようやく一息ついた。
たいていのバイトの面接時には履歴書を用意しておくものだけど、今回のバイトには履歴書は不要だった。
おじさんが面接準備のために部屋をでてからあっという間に五分が経過した。
遅いな、と思いつつとりあえずたいして広くない空間を見回してみる。
部屋には何台かのオフィスデスクと観葉植物がすみっこにあるぐらいでこれといった特徴はなかった。
ただ蛍光灯がきれかかって明滅しているものしかないせいか、妙な不気味さが部屋中にただよっていた。
結局おじさんが部屋に戻ってきたのはさらに十分がたってからだった。
おじさんはワタシの対面の位置にパイプ椅子を置いてそこに腰をかける。
「今日はお越しいただいてありがとうございます。
それではさっそく面接に入りたいと思います。
単刀直入に言いますがこのバイトは普通のバイトとは少々異なります」
「と、言うと?」
「あなたには出会い系サイトのサクラをやってもらいたいのです」
あの女の子の言ったことはどうやら本当だったらしい。
背中の毛穴が開いてジワリと嫌な汗が背筋をゆっくりとなぞるのを感じた。
やっていただけますか?」
相変わらずおじさんの口調は穏やかだったし、表情もやわらかいままだった。
それにもかかわらずその声に霜がおりたような冷たさを感じたのは単なるワタシの勘違いなのだろうか。
なんて答えればいいのか迷っているワタシにおじさんは言った。
「出会い系のサクラってどういうものかと言いいますと。
ようするにあなたにはうちのサイトの会員になってもらい、男性会員の人とメールのやりとりをしてもらいたい。
ここまでは意味がわかりますか?」
実のところこのサクラというものについては多少調べたので、おおまかにはどういうものか理解していた。
「だいたいはわかります。そういう話も聞いたことあるんで。
ようはワタシがとにかく色んな人にメールをばらまいて食いついた人にはメールしてポイントを消費させて購入させる。
そういうことですよね?」
「話が早くて助かります。
しかし、うちがバイトにしてもらうのはそれだけではないんです」
「べつにそれだけだったらわざわざ女性を雇う必要はないんですよ。
男性でも女性になりきってメールすることはできますからね」
「じゃあ、ほかになにをするんですか?」
「実際にひとり、あるいはふたり、場合によってはそれ以上の男性会員にあってもらいたい」
さすがにこれにはおどろかずにはいられなかった。
たぶんワタシのおどろきは露骨に顔に出てしまったのだろう。
おじさんはさらに説明を続けた。
「近年、出会い系の評判は某大型掲示板やそのほかのネットサイトで情報がかなり手に入るようになっています。
そういうわけでちょっと前のように騙される人間というのが減っているのです。
そのためこの手の会社は競争が厳しくなっているだけでなく、ほとんど大手がシェアを占めているんです。
そこで働いているサクラには一度きりという条件で実際にサイトを利用している人と接触してもらいたいのです」
「は、はあ……」
さすがにどういう返しが正しいのかわからずワタシはそう言うことしかできなかった。
ただワタシのこのバイトに対する天秤がやらない方へとかたむいたのは確かだった。
「この手のバイトはごまんとありますが、実際に会うということをするバイトはおそらくないでしょう。
しかし、近年の状況を考えますとこの方法こそが我がサイトの発展、しいては我が社の発展に一番いいはずなのです」
「そ、そーなんですか」
そんなことを言われても、ねえ?
さすがにネットでやりとりしただけのニンゲンといきなり会うのはどうなのだろう。
どんなニンゲンかもわからないのに実際に会うなんて危険すぎるのでは?
「今、あなたがなにを考えられているのか私にはだいたい検討がつきます。
そこでですね。私どももそれ相応の報酬を用意しようと思います。
がんばりしだいでは我々は月給として百万以上支払ってもいい」
一瞬なにを言われたのかわからなかった。
十秒ぐらいたってようやくワタシの脳みそは面接官の言葉を飲みこむことができた。
雷が脳天を直撃したかのような衝撃にワタシは面接中なのに大声を出してしまった。
「え、ええぇ!? ほ、ホントに言ってるんですか!?」
「嘘は言いません。リスクはもちろんありますので妥当な給料だと思います」
月に百万円もらえるかもしれないという事実は、ワタシのこのバイトに対する不安をかき消すのに十分だった。
「どうですか? やっていただけないでしょうか?
バイトの数はまだまだ不足していますので少しでも多くの方にこの仕事をやってもらいたいのです」
「は、はい。ワタシでよければ……ぜひ」
ワタシはあっさりと了承してしまった。
百万という数字はワタシのような女子大生などあっさりと籠絡させてしまった。
「ありがとうございます! お互いにがんばっていきましょう」
握手を求められたのでワタシは右手を差し出した。
ワタシの手を握るおじさんの骨ばったそれは妙に汗ばんでいて不快だったけど、それさえもどうでもよくなるぐらい気分が高翌揚していた。
4
基本的にこのビルのパソコンと自分のケータイを使って仕事をするらしい。
シフトは最低週一日からでいいということで、時間の融通もきくようでありがたかった。
サクラをするにあたりマニュアルをもらいその説明も受けた。
まあしかしイロイロと相手を騙すための手口があるものだ。
ばらまくメールの例文やら、サイトへの誘導のしかたやらメアドの交換の拒否方法やら。
約一時間ぐらいの説明をおじさんから受け終わりもう帰るだけかと思ったが、
「説明は以上で終わりますが最後にどうしても守っていただきたいことがあります」
「なんなんですか?」
「最後にあなたには誓いをしてほしいのです」
「ちかい?」
「ええ、誓いです。私についてきてください」
ワタシの返事を待たずに面接官はすでに動き出していた。
面接官についていくまま部屋を出て階段をあがって最上階まで行く。
最上階はそれまでの階とはちがい部屋に通じる扉がひとつあるだけだった。
「これからここであなたには宣誓をしてもらいます。今日はこれをしてもらえば終わりです」
目の前のおじさんがふり返る。
けれども目もとは少しも笑ってなくて、ワタシは黙ってうなずくことしかできなかった。
扉が開かれる。蝶番の軋む音がやけに長く聞こえた。
「さあ入ってください」
言われるままワタシは面接官とともに部屋に入った。
部屋は真っ暗だった。
てっきりすぐ照明をつけてくれるのかと思ったが面接官はいつまでたってもなにもしない。
深い闇に全身塗りつぶされるような錯覚におそわれてワタシは慌てて言った。
「あ、あの! 明かりつけないん……」
ワタシの言葉は最後まで続かなかった。
部屋のど真ん中に人形があることに気づいたのだ。
絵の具がにじむように深い闇の中から現れた等身大の人形は木製のイスの背もたれに全身をあずけるように腰掛けていた。
その人形は真っ白なワンピースを着ていて真っ暗な部屋の中でも異様な存在感をはなっていた。
長すぎる黒髪の下の顔は、その前髪のせいで見えなかったけどそれでも異様に人形の肌が白いのだけはわかった。
投げ出された手足は痛々しいまでにか細くて触れただけで折れてしまいそうだった。
いったいなんだこれは?
部屋の中に明かりらしきものは見当たらない。なのに気づけば人形の姿はワタシの目に鮮明に映っていた。
闇に目が慣れたとかではない。仮にそうだったとしたらワタシの前にいるはずのおじさんも見えるはずだ。
実際には面接官のおじさんは真っ暗闇の中に埋没してしまっている。
得体の知れない恐怖が足もとから這いあがってくる。
吸い込んだ息がノドの奥で音を立てた。
全身の産毛が逆立って肌が粟立つ。
悲鳴がノドを食い破ってしまいそうになるのを必死にこらえる。
「それでは『彼女』にひとつだけ、今から私が言うことを誓ってください」
この空間から一刻も早く出たくてワタシはただうなずく。
これだけ暗い空間ではどんなにうなずいたとしても見えるはずもないのに。
「誓いはただひとつです。この仕事において『恋をする』ということをしないと誓ってください」
「わ、ワタシは恋なんてしません!」
意味なんて理解できないまま間髪いれずにワタシは叫んだ。
声はみっともないぐらいふるえていた。
「あなたは『彼女』の前ではっきりと誓いました。その誓いをくれぐれも破らないように」
話している内容は異様なのに声は機械のように淡々としている。
「それでは出ましょう。
『彼女』は人と同じ空間にいることをあまり好まない」
そう言われてもワタシの四肢は血を抜かれたように力が入らなかった。
不意に光が差し込む。面接官の人がいつの間にかワタシの背後にいて扉を開いてくれていた。
「早く出てください」
「あ、はい……」
灯火に吸い込まれる虫のようにワタシはふらふらと光指す出口へと向かった。
背中に得体の知れない視線を感じながら。
オリジナルで思いついた話をダラダラ書き連ねてく
今日の夜から再開
そのあとのことはよく覚えていない。
本能があの人形についての記憶に霞をかけているようだった。
ビルから出る直前。
自分と同じぐらいの歳のオトコがビルの入口に入ってきてすれ違ったが挨拶したかどうか、その記憶さえ曖昧だった。
『とりあえず家に帰ってからでいいので教えたアドレスからサイトに入って登録しておいてください』
はじめて顔を合わせたときと別れのときの面接官の印象はまるでちがった。
しかしそれ以上に気になることがあった。
ワタシはてっきりあのおじさんは常軌を逸した変人で、あの空間にいてもなにも感じてないのかと思っていた。
だが部屋から出たおじさんの顔は紙のように真っ白で額には脂汗を浮かべていた。
ふるえる唇は血の気が失せて紫色に変色していた。
『くれぐれも誓いを破らないように。破ったときはそれ相応の報いが待っています』
部屋を出た直後おじさんはそう言った。
ほとんどそのときのワタシの耳には入ってなかったけど今思えばきちんと言葉の意味を聞いておくべきだった。
「それ相応の報い、か」
新手のおどしとも取れた。
この手の会社が捕まったという話はネットサーフィンをしているときに目にした。
口外をすることは契約書においても禁止されていたが、しょせんはバイトだ。
喜々としてこの仕事のことを話すバカがいてもおかしくはないだろう。
つまりあの人形の前でした誓いも、これからワタシが純粋なサイト会員というカタチで出会う人たちに対して、迂闊なことを口にさせないための処置というふうには考えられないだろうか。
懇意の間柄になって秘密をぺらぺらしゃべらせないための処置なのかもしれない。
どこかおかしい気がしたけどそう結論づけてワタシは自分を無理やり納得させた。
もはや用事はなかったし、人であふれたこの街にいる理由はなかった。
普段のワタシならさっさと帰宅しているところだった。
けれどもワタシの五感は錆びついたかのように鈍くなっていて、自分の世界のあらゆることが霧がかかったようにぼやけていた。
街のありとあらゆる音の洪水もどこかくぐもって聞こえた。
ふとあの人形が脳裏をよぎる。
細い手首。
白すぎる肌。
ワンピース。
長い髪。
見えない顔。
あの不気味な人形は間違いなくはじめて見たものだった。
それにもかかわらずワタシはどこかであの人形を見た気がしてならなかった。
そもそもワタシはこのバイトをやめるべきなのではないか?
バックレてしまえばいいんじゃないか?
あんな得体の知れないものを飼いならしている職場などで働く必要はあるのか?
「あのー、すいません」
音にあふれかえった街の中でも澄んだ声ははっきりとワタシの耳に届いた。
ふりかえった先には英語の講義で同じ席に座った女の子がいた。
ダボっとした赤いセーターと青いニット帽、化粧っ気のほとんどない白い顔。
妙な芋くささを漂わせた少女は愛嬌たっぷりに破顔した。
「わあ! やっぱりあのときの人ですよね?
私のこと覚えていますか? 大人数英語で隣でしゃべったじゃないですか」
「あ、ああ……覚えてるよ」
「偶然ですね。もしかして、と思って話しかけたんですけど本当にあのときの人でびっくりしました。
って、ごめんなさい。もしかして今取りこみ中だったりしました?」
「ううん、そういうわけじゃないんだ。ただびっくりしただけだよ」
秋葉原であったこともそうだし、たった一度少し話しただけの相手にわざわざ話しかけに来たことも。
「今日はどうされたんですか?
あ、ちなみにワタシはフィギュアを見に来たんですけど。アキバにはよく来るんですか?」
そう言って女の子は小さな手にもった『アニメイト』と書かれた袋を嬉しそうに見せてきた。
「え? あ、いやいや、ただバイトの面接に来ただけだよ」
急にまくしたてられてワタシはうっかり本当のことを話してしまった。
「バイトの面接? ああ、この前話してたバイトのですか?」
「うん、それそれ」
「そういえば結局どんなバイトだったんですか?」
「話してもいいんだけど……もしこれからヒマならミスドとかスタバとかどこでもいいけど入らない?
立ち話もなんだしどっか入って話そうよ」
「そうですね、そうしましょう。 ミスドならすぐそばにありますし。そこでいいですか?」
「うん、近いならそこでいいよ」
ワタシはいったいどこまでこの女の子に話そうか、アタマの片隅で考えていた。
海馬にこびりついた人形の顔がふと笑った気がした。
6
「本当にそういうバイトってあるんですね」
ミスタードーナッツは中央通りと呼ばれる大きな通りに面していたけど、店内はさほど混んではいなかった。
ミスドの店内は決して広くないものの空いてる席もそこそこにあったのでワタシたちは一番奥のはじっこの席に座って話すことにした。
女の子の名前はレミというらしい。
あのビルからここまでの道のりは、近いと言うわりには意外と距離があったのでお互いに自己紹介をしながら歩いてきた。
ちなみに。
ミスドの中央通りをはさんだ向かい側にはアニメイトというショップがあるらしく、レミはさっきまでそこでアニメグッズを買いあさっていたらしい。
「そうだね、ワタシもけっこうびっくりしてる」
ワタシはレミにバイトの内容をほとんど話してしまった。
まあ、この素直そうな女の子ならワタシがだまっておいてと頼めば大丈夫だろうという無根拠な確信があった。
もっとも人形のことにかんしてはこれっぽっちも話そうとは思わなかったので言ってない。
「それにお金も、本当だったらとんでもない額ですよね」
「うん、ホントだったらヤバイね。なんていうか夢が広がるよね」
「というか私にこのバイトの話、しちゃってよかったんですか?
あまりよくないような気がするんですけど」
「ホントは言っちゃだめみたい。まあ真っ当に仕事してますって胸はれるような内容でもないしね。
まあだからほかの人にはナイショね。ふたりだけのヒミツ」
「はい、まかせてください。私、がんばって秘密にします」
そう言ってレミはおいしそうにチョコファッションにかぶりついた。
彼女の前にはほかにもチョコリングにポンデリング(黒糖)が載った皿があった。
誰がどう見ても細いはずなのによく食べるなあ、と感心して見ていると、
「どうかしました?」
と、首をかしげた。なにげない仕草だったけど自分がオトコだったらこの瞬間に惚れてしまっているかもしれない。
そうワタシに思わせるぐらいには愛らしい仕草だった。
ワタシはオールドファッションを頬張りつつ聞いてみた。
「このバイト……やるべきだと思う?」
「わかりません。やっぱり安全なバイトとは思えませんし」
「まあたしかにね。それに、胸はって堂々とできる仕事ってわけでもないしね。
そういう意味ではやるべきではないのかも」
「でも……」
レミはそこで言葉を切った。
冬の湖水のように穏やかに澄んだ瞳にはワタシが映っていて、ワタシは無意識に自分自身から目をそらした。
「え?」
「私にはあなたがバイトをしてみたいように見えるんですよね。
だってそうでなかったらわざわざ私に聞かないと思いますし」
またレミと目があった。レミの瞳の中のワタシはどこか戸惑っているように見えた。
たぶんその理由は出会って間もない人に本心を見抜かれたからなのだろう。
なぜか顔が熱くなるのを感じてワタシはことさらいいかげんな口調で言った。
「あー、まあそーなのかもね。うん、じゃあまあやろうかなあ?」
「そうですよ。もしそれになにかあったら、よかったら私に相談してください。
力にはなれないかもしれないけど愚痴ぐらいなら聞きますよ」
はにかんだレミの唇のはじっこにはドーナッツの食べカスがついてたけど、あえてワタシは指摘しなかった。
けっこう長い時間話していたせいか、少しお尻が痛かったけど気分はよかった。
「今日は楽しかったです。またよかったら行きましょうよ」
オレンジ色の太陽を背後にしているせいなのか、もしくはそれ以外が理由なのかは知らないけどレミの笑顔がワタシにはまぶしかった。
「うん、また授業であったときに話そ」
少し別れが惜しかった。ひさびさに充実したと思える時間を過ごせたからだ。
「ワタシも……今日はホントに楽しかった。じゃあね」
最後にそうつけくわえてワタシはきびすを返した。
一日の終わりを告げるようにビルの間から見えた太陽はどこか寂しそうだったけどオレンジ色に染まった街はすごく儚げで、ホントにキレイだった。
キライな雑踏やその喧騒もなぜだかワタシの気持ちを高翌揚させて、ワタシの足どりを軽くした。
特に意味のないつぶやきだった。
逢魔が時。
黄昏時。
夕刻。
幽霊が出る。
魔物が出やすい。
怪しいものが現れる。
「……っ!?」
不意に首筋が焼けるような強烈な視線を感じてワタシは足をとめた。
視線に質量があったら間違いなくワタシの首にはドーナッツのような風穴ができていただろう。
あの人形を見たときと同じ感覚だ。
ワタシは反射的にふりかえった。
オレンジ色のとばりを背に輝いていた街は薄い闇に覆われて、太陽は光の残滓を残してビルの影に消えてしまっていた。
一瞬のうちに景色が変わってしまっていた。
それでも。
ほんのわずかの間に姿を変えた街の中で変わっていないものがあった。
地面に写る雑踏の影法師にまぎれてワタシだけを見ている少女。
「レミ……」
いや、天真爛漫を絵に書いたような彼女とあの人形が関係あるわけがない。
まして彼女からあの人形と同じ得体の知れない不気味な感覚を覚えること自体おかしい。
なぜ彼女が別れた場所から動いていないのかということに疑問をもつ余裕すらなく、ワタシはただ呆然としてしまう。
レミの顔は重い前髪のせいではっきりとうかがうことができなかった。
けれども唇が三日月の形に割れたのだけはわかった。
「レっ……」
意味もわからずとっさに彼女の名前が口から出かけた。
やたらと大きなリュックを背負った巨漢と肩がぶつかる。
ここは秋葉原、都会だ。道のど真ん中に突っ立っていてたらすれ違いざまに接触してしまうのは当然だった。
もう一度レミがいた場所を見る。
流れる人ごみの中に彼女はもういなかった。
家に帰ってすぐにシャワーをあびてベッドに腰かける。
メイク落としと洗顔料で突っぱねた顔に化粧水と乳液を塗りこんでワタシはいったんベッドに腰かけた。
乳酸が溜まってむくんでしまった足にも同じようにして軽くさするようにマッサージをほどこすと、少しラクになった気がした。
人がうじゃうじゃといる都会を歩くのはそれだけで体力を無駄に消費する。
ようやくワタシが一息つくころには目覚まし時計の針が八時をさそうとしていた。
食欲はいまいちわかなかったのでコンビニで買ったコールスローとカフェラテで夜ご飯をすましてさっそくバイトの下準備をしてみることにした。
登録しておいたアドレスからサイトに入る。
最初にオトコかオンナかの性別を選択するところから始まる。当然オンナのほうを選ぶ。
さらに進むと細かいプロフィールの設定画面に移った。
名前、年齢、職業、趣味、身長、体重、スリーサイズ、好みの男性のタイプ、エトセトラ。
設定するプロフィールの項目の多さに早くもワタシはスマホを放り出しそうになった。
とりあえず少しだけ休憩してからワタシはプロフィールを丁寧に作成した。
冷静になって考えればこんなことで百万がもらえるなんて恐ろしく贅沢な話である。
多少数字を盛ったプロフィールが完成した。
そのあと自己ピーアール文を打ってワタシは登録を完了させた。
「さて、これでしばらく待ってればいいのかな……」
ワタシの部屋は七畳のワンケーでそこまで広くないものの、アパート自体は線路沿いにあって駅からは徒歩三分しかかからない。
しかも中央線沿いで新宿や中野、吉祥寺、立川といった栄えた場所も近く便利極まりない。
もっともいいことばかりではないし、そこそこ厄介な問題点もこのアパートは抱えている。
ボロアパートは駅から近すぎるうえに防音設備はずさんそのもの。
そのため電車が横切るたびに建物は揺れるわうるさいわで、そのことに関してだけは若干このアパートを選んだことを後悔してる。
電車の走行音に続くようにスマホがメールが来たことを告げる。
もしかして。
スマホの画面を見てみると予想通り、サイトの男性会員からメールが来ていた。
「はえー」
まだサイトに登録してから数十秒ぐらいしかたってないのに、エモノはさっそく罠にむしゃぶりついたようだった。
ほとんど呆れた気分で画面を見てみてまたもひとりごとが出そうになってしまった。
メールの着信は一件ではなく四件だったのだ。
ルアーもエサもついてない釣り竿でクジラでも引き上げてしまったような名状しがたい気分だった。
釣りなんてちっちゃいころに釣り堀でやったぐらいしかないけど。
さっそく送られてきたアプローチメールを見てみる。
内容はどれも似たり寄ったりだった。
はじめましての定型分に続いて、いきなり会わないかとか、っていうのが一件でそれ以外のメールはやりとりしませんかというものだった。
とりあえずワタシの食指を動かしそうなメールはなかったので誰にも返信はしなかった。
「ていうか、いきなりすぎて対応できないっつーの」
どうして登録してからほとんど同時にメールが来たかというと、このサイトは新規の会員がわかるようになっている。
こういったサイトに慣れていない人間のほうが扱いやすいだろうし、オトコが新規に飛びつくのは当然のこと。
……という風にあのおじさんからは聞いている。
少し気の毒かな?
いきなりの新人さんがサクラで申し訳ない、とわりと罪悪感を感じた。
メールをするたびにポイントが減っていく。
ほかのことはすべてタダだけどだとしても何度もやりとりするにはポイントをかなり消費する必要がある。
だからこそオトコはさっさと会うなりメアドを交換してサイトの縛りから解放されたいのだ。
もっともオンナはすべてにおいてタダなのでやりたい放題だった。
そしてワタシのバイトの目的は相手のオトコにできるかぎりメールをさせてポイントを購入させること。
つまり本来ならばワタシはこの四人にすぐにでもメールを返すべきなのだ。
「仕方ない、やるか」
このサイト、実は写真を登録することができる。
今のワタシは化粧も落として風呂に入ったあとなので、写真を撮る気はないけど次の勤務までには写真登録も済まさねばならない。
知り合いにばれたらどうしようと、思ったが百万のことを思えばそれぐらいのリスクは覚悟しなければならないだろう。
ワタシはさっそく返信のメールの作成にとりかかった。
バイト初出勤の日、電気街は生憎と曇りだった。
浮かんでるのが不思議なほどに黒々とした雲を敷き詰めた空はワタシをより一層憂鬱にさせた。
昼の秋葉原はこの前来たときと変わらずたくさんの人でにぎわっていた。
しいて前回とちがう点があるとすれば、道ゆく人々の多くが傘をもってることぐらいだろう。
バイトの面接から四日間がたったけど、ワタシはその間にワタシは時間があるときはひたすはスマホをいじってあらゆるオトコとコンタクトした。
最初こそ良心を紙ヤスリで磨り減らすような呵責を感じていたけど、サイトでやりとりをしているうちにそんな感覚は無意識の底に沈んでいった。
結局ワタシが多額の金を求めるようにこのサイトの連中も自分の欲望の行き場を探してるだけなんだ。
フラストレーションの捌け口を見えない画面の向こう側の相手に求めてるだけの連中。
その数の多さにワタシは吐き気すら覚えた。
「まあ世の中バカばっかということだよね」
雨が降る前になんとかビルに到着した。
バイト先であるビルの通りはほとんど人がいないので、ワタシのひとり言を聞く人間はいない。
ビルの階段をあがってホコリまみれの廊下を経由して仕事場の扉をあける。
少し型の古そうなデスクトップ型のパソコンとオフィスデスクが数台あるだけの簡素な部屋にはこの前のおじさんしかいなかった。
おじさんはパソコンをいじってなにかをしていた。
ワタシに気づくとパソコンをいじっていた手を止めた。
「おはようございます」
「おはようございます」
すでに太陽がてっぺんでふんぞりかえる時間だったけどあいさつは朝のそれだ。
簡単な仕事の確認とアドバイスを受けてワタシはパソコンと向きあった。
これからバカなオトコどもを釣るために、とびっきりのエサとなるメールをこのパソコンを使ってバラまくのだ。
文章を打ちこんでランダムにメールを送信。
エモノがエサにかかるのに時間はほとんどいらないだろうがわずかな時間を利用して、やりとりが途中のままになっていた相手にメールを送る。
そういえばこのビルにいる人って今どれぐらいなんだろ?
ふとささいな疑問が浮上して打鍵した手がとまる。
まさかワタシと、面接官のおじさんだけなわけはない。
おじさんの口ぶり的におそらく、そこそこに従業員はそろえてあるはず。
一瞬だけこのことについて質問しようかと思ったけど、エサメールに釣られたオトコからの返信が来たのでワタシはそちらに集中することにした。
数時間、ほとんどルーチンワークのような作業を黙々とこなしていたけどさすがに集中力切れしたのでワタシはパソコンの画面から目を離してのびをした。
特に一番疲れが溜まった目頭を揉んで、凝りかたまった筋肉をほぐしてやる。
「なかなかキミは人を騙す才能があるみたいですね」
「へ?」
優しげな声でひどく失礼なことを言われた。
もちろん声の主はおじさんで、そのおじさんは微塵の悪気も感じさせない穏やかな表情でワタシを見ていた。
ほめられてここまで複雑な気分になったのは初めてだった。
「まあ、なんかそーみたいですねー」
「あなたの記録をワタシのパソコンから見させてもらってますがすこぶる順調のようですね。
メールの文面もさることながら手際も悪くない。
効率よく相手を見つけ出してメールをしていますね」
「そんなに褒めたおされるとワタシ、調子に乗っちゃいますよ?」
わざとらしくおどけてみた。
ほめられること自体苦手だったし、この人と話すのはどうやらワタシにはけっこうなストレスのようだった。
胃がキリリと痛むのがわかった。
「この調子ならここに来る回数を減らしてもらっていい。
もちろん、仕事自体はしてもらうけどね」
「いいんですか? まあアキバってそんなに近いとこってわけでもないからありがたいですけど」
「私としてはこの会社の利益になるならなにをしてもらっても構わないと思ってるからね。
それに遠いところから足繁く通ってもらうのは心苦しいからね」
「はあ……」
「私の望んでいたノルマをキミはすでに超えている。
なんなら今日はもう帰ってもらってもいいよ」
ねがってもない展開だった。
こんなほこりっぽいところにはいつまでもいたくない。
「……」
「キミには再び彼女に誓いの言葉を述べてもらいたい」
信頼の証としてね。
彼はそう言うとイスから立ち上がってワタシに、ついて来てくださいと歩き出した。
ワタシは半ば諦めの境地でついて行く。
二度目になれば少しは慣れるかと思ったけど、あの人形のいる部屋の扉の前に立つと急激に体温があがって鼓動が早くなるのを感じた。
おじさんの手が扉のとってを握る。
ゆっくりと開かれる扉。
蝶番の悲鳴。
二回目の人形との邂逅。
墨汁で塗りつぶしたような真っ暗な空間。
以前体験した感覚がそのままよみがえってワタシは早くもこの場から逃げ出したくなった。
人形が不意に視界にあらわれる。
以前は冷静さをまるで失っていたためわからなかったが、今回はワタシはその怪奇な現象に気づくことができた。
てっきり人形が暗闇から現れるように見えていたのは、暗闇に目が慣れてもともと部屋にあったそれを認識できるようになっただけと思っていた。
だが今ワタシが見たかぎりではわら半紙に墨汁がにじむように、文字通りあらわれたというふうにさ見えなかった。
「それでは誓いを述べてもらいます。ごくごく当たり前のことを誓ってもらいます」
声のするほうへ視線を移すが、あるのは真っ暗闇だけだ。
つかもうと思えばホントにつかめてしまいそうな濃密な闇の中でワタシは人形を観察する。
「あれ……?」
なにか違和感のようなものを覚えてワタシは眉をひそめた。
なにか以前とはまったく異なるものを見出した気がしてワタシは人形をできるかぎり観察する。
間違い探しは数秒経過することなく一瞬で終わった。
以前ワタシが来たときに着ていたワンピースと今着ているワンピースの色がまったくちがうのだ。
以前は首もとだけ白い真っ赤なワンピースだったのに対して今回はパステルグリーンのものになっている。
しかしこのちがいが意味するところがなんなのかワタシにはわからなかった。
そもそも意味なんてなくて単なる人形の着せ替えという可能性もあるが。
「話を聞いていますか? きちんと話を聞いていないと後々後悔しますよ?」
「……すみません」
「あなたに新たに誓ってもらうことは『与えられた仕事をきちんとやる』ということです」
この誓いにいったいどんな意味があるのか聞くだけの勇気はワタシにはなかった。
いつの間にか口の中の水分は干上がっていて、渇いた喉は息を吸うだけで奇怪な音をたてた。
掠れた声で自分に言い聞かせるようにワタシは言った。
「ワタシは……まじめに仕事をします」
「その誓いに恥じない働きを期待しています。
それでは出ましょうか」
澱のように堆積した暗闇に足をとられるような錯覚を覚えた。
それでも前よりはきちんと歩けていたし幾分かは冷静だったと思う。
ワタシは部屋を出る直前とっさにふりかえった。
けれどもさっきまでワタシと対峙していた人形は漆黒の中に溶けてしまっていた。
それでもねっとした舐めるような視線をワタシは首筋にはっきりと感じていた。
部屋を出ておじさんにあいさつをしてワタシはさっさと退勤することにした。
やっぱりおじさん以外には誰にも会わなかったが、そんなことよりもこのビルから逃げるほうが今のワタシには大事だった。
ビルの玄関を出る。
どうやらワタシがビルに引きこもってよろしくないことにウツツをぬかしているうちにほとんどの雲は次の場所へ向かったらしかった。
天気は回復したのだけど、時間が時間なだけに太陽はすでにかたむき出していて陽射しも比較的柔らかいものになっていた。
それでもずっと暗い空間にいたからだろうか。
太陽の光がいつもよりワタシにはまぶしかった。
太陽のまぶしさに無意識に目をほそめてワタシは視線を下へさげようとした。
あまりにもよすぎるタイミングで彼女がワタシの目の前を横切った。
ニット帽からこぼれる陽の光を弾くように波打つ濡れ羽色の髪。
気味悪くすらあるロウのように白い肌。
触れるのをためらってしまいそうになるほどの華奢なカラダつき。
そして、
風をはらんでふわりと広がるパステルグリーンのワンピース。
悲鳴をあげなかったのはほとんど奇跡だった。
全身の血が音をたてて引くのが聞こえてくるようだった。
気になっていることがあった。
ワタシがこのビルでの面接を終えて出たときに、なぜレミはここにいたのかという疑問。
彼女が話そうとはしなかったのでワタシはあえて聞かなかったが。
そして別れた直後に感じた強烈な視線の正体は……。
「……」
そしてたった今彼女はこのビルの前を横切って行った。
地方出身の単なる田舎少女。
彼女はホントにただそれだけの存在なのだろうか。
ワタシはパステルグリーンの背中が人ごみにまぎれて消えるのを眺めることしかできなかった。