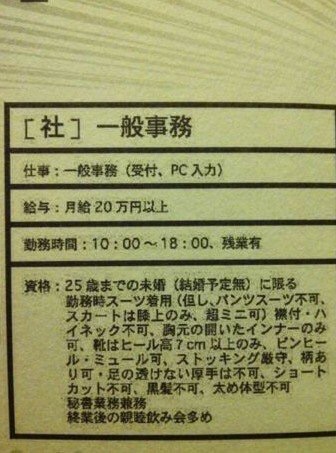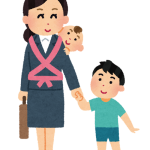プラモが積み上がった部屋で生涯を閉じた末期がん独身男。
sssp://img.5ch.net/ico/nida.gif
独り身、プラモデルが所狭しと並ぶ自宅で生涯閉じる…残された時間「病院よりも家で自由に」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180905-00010000-yomidr-soci
高齢化が進み、日本は年間130万人以上が亡くなる「多死社会」になった。多くの人が住み慣れた家での最期を望むが、かなえられていない。九州・山口・沖縄では、特に少ない傾向にある。自宅、施設、病院。それぞれの場所で悩みながら選択していく本人や家族の姿から、最期のあり方を考える。
福岡市博多区。古くからある住宅街の一角に、その家はあった。
まだ新しい2階建て。5月、招き入れられたリビングには、野球やサッカーの雑誌が積まれ、無線操縦の車のプラモデルが所狭しと並んでいた。この家に一人で住む田中雄二さん(仮名)の趣味の品々だ。
末期の直腸がんを患う田中さんは、最期を過ごす場所に、我が家を選んだ。妻子はなく、高齢の両親は介護施設に入居。「あと何か月生きられるかわからないけど、できれば、ここで逝きたいね」
この言葉から1か月後。田中さんは、この家で61歳の生涯を閉じた。
40歳を過ぎて結婚し、離婚…ステージ4の直腸がんと診断され
福岡市内の高校を出て大学に進学。デパート勤めなどの後、自宅でインターネットを使った雑貨販売を始めた。40歳を過ぎて結婚し、離婚。家は2012年、両親と自分の「終(つい)の住み家」にしようと建てた。
ステージ4の直腸がんと診断されたのは、それから2年後。すでに、がんは肺やリンパ節に転移していた。
九州がんセンター(福岡市南区)への入院3日目、隣のベッドの男性が退院準備を始めた。「女房と、うまいもんを食べに行くんだ」。抗がん剤が効かなくなり、手の施しようがなくなったとは、後で知った。でも、その表情は穏やかだった。
自分にその時が来たらどうするか――。「残された時間は、家で自由に過ごせたら」。闘病仲間とこの先のことを話すうち、そう考えるようになっていった。
「これ以上の治療は難しい」と告げられ…
通院治療に移っていた今年2月。医師から「これ以上の治療は難しい」と告げられた。抗がん剤の副作用で、食事はのどを通らない。痛みも強く、立ち上がってもふらつく状態だった。
「一人の家は難しい。ホスピスへ行くしかない」。気持ちが固まり始めた時、一人の医師を紹介された。
同市南区で在宅療養支援診療所の「清水クリニック」を開業する清水大一郎さん(70)。「それぞれの価値観や人生観を認め、支え、見守ることが務め」と考え、20年近くがん患者を自宅で看取(みと)ってきた在宅医だ。3月から週1回の訪問診療で痛みを取り除いてもらった。24時間対応の訪問看護ステーションとも契約し、週に2回の訪問を受けた。
病はしばらく小康状態が続いた。「急変したときの不安はある。でも、病院よりも家の方が、自分の好きなことをして生きられる」。好物のピザを食べ、「これも終活だ」と、少しずつ家の中の整理を始めた。